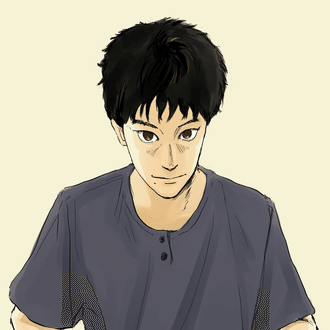時の差婚(7000字)
作り笑いに気付いたのはそのときが初めてだった。
小さな笑い声を上げた彼女は、きっと泣いていた。
僕が定年退職した頃、一般人もタイムマシンを使えるようになった。
高校生のときに知り合った妻、チサも同じ年に仕事を辞めた。家族にも恵まれた。退職金も十分にある。僕は自らの余生に何ら不満があるわけではなかった。
ただ、過去にある未練があった。
あれは高校2年のバレンタインデーだ。毎年僕には無縁なイベントだった。だがその年は最悪だった。
告白の失敗。
誰にでもあることだ。それはよくわかっている。だがそもそも恋愛経験そのものが少なかった僕にとって、それはあまりに惨めで、大きすぎた。
既に半世紀も前のことではある。当時のネットスラングで言うところの「コミュ障の黒歴史」として、記憶の扉を閉してしまうのが健全だろう。
ところがこの時代にはタイムマシンが普及してしまった。
誰かが言った。道具は身体の延長だと。
僕の両親が学生の頃、遠くの相手と簡単に話せる道具で遠距離の恋愛は容易くなった。僕は、過去の相手に会いに行ける道具で、 あの子にもう一度告白するのだ。
タイムマシンを一般人が購入するには、特別な資格や審査が必要とされているらしい。そのためほとんどは国営の病院や専用の施設に設置されている。 僕はインターネットで予約サイトを開いた。
タイムマシンは、過去の自分に今の自分の意識を転送することができる。過去の自分を操ることで、過去やそれから続く未来を変えられるようだ。
使用料は1時間につき3万円。退職金で貯蓄は十分にあったが、あまり使うとチサに勘付かれる。本当は1週間でも1ヶ月でも過去に戻ってあの子の前で格好をつけたかった。だがそもそもやり直したいのは「告白」であって「恋」ではない。はっきりと気持ちを伝えられたらそれで十分だ。チサには黙って貯めていた金で10時間分を買った。
予約してからの毎日は一瞬で過ぎた。今日は待ち望んだその日だ。街で一番大きな病院へ向かい、受付番号を渡した。
指定された部屋は板のようなもので3つに区切られており、その1つずつにタイムマシンが置いてあった。見た目は機械仕掛けの棺桶といった感じだ。カプセル型のベッドにも見える。
1つだけ蓋が開いているのが僕の予約したものだ。説明で聞いた通りまず服を脱いで隣のカゴへ入れた。過去に戻っている間も肉体は代謝を続けるからだ。タイムマシンに入り上向きに寝た。すぐ横のタッチパネルを押すと蓋が閉じる。次は頭と股間に装置を取り付けた。下の方の装置は先ほどと同じ生理的な理由だ。
タッチパネルで戻る日時を指定する。2018年の2月14日、朝の8時から夕方6時。
赤いスタートボタンを押すと、頭の装置が機械的な振動音を出した。
一瞬のち、僕は意識を失った。
視界の全てが真っ白だ。
やがて景色に線が入り混じり、それらは廊下の風景になった。
一瞬分からなかった。何故学校の廊下で視界が霞んだのか。
その気付きは感動とともにやってきた。
そうだ。僕は過去へ戻ってきたのだ。
上着のポケットに手を当てた。渡すべきチョコの感覚がそこにあった。
僕の隣を数人の生徒が通り抜けていった。そのうち1人の男子が僕の方へ振り向いた。
「おう斎藤、おはよう」
「…お、おはよう」
斎藤は僕の名だ。ノスタルジーに浸っていて反応が遅れたが、声変わりの途中の僕の声が喉から出た。彼は僕に向かって顔をしかめた。
「何でこんなところで立ち止まってんだよ、斎藤。もっとちゃんとしないと、またお前…」
確か彼の名前は高松。クラスのまとめ役だ。「普通」と違った僕をクラスの輪に入れようと、彼はよく指示を出してきた。
「まぁいいや。とりあえず教室行こうぜ。それより斎藤、ちゃんとヒゲ剃ってきたんじゃん。寝グセも直ってるし」
うるさいな。そう思っていた気がする。「僕はお洒落に興味がないから」と言うと、彼はいつも「お洒落と身だしなみは違う。お前のそれはマナー違反だ」と返してきた。
学生の頃は今と身長が違うからだろうか。何だか歩きにくい気がする。教室へ入るとき、ドアの端で足をぶつけてしまった。近くにいた女子の苦笑いを消すように、高松が笑う。
「おいおい斎藤、大丈夫かよ!?お前って本当ドジだな」
高松の笑い方は、親しい友人が小馬鹿にし合うようなものだった。少なくとも目の前の女子とは違う種類のものだった。つられて周囲の女子も笑顔を浮かべる。
高松のそれは優しさかも知れない。だが僕は、彼の目が笑っているかどうか判断できるようになっていた。彼の優しさは、それに気付ける今となっては残酷さでしかなかった。
うつむき気味に前を見ると、2人の女子生徒が目に入った。教室の前列に並んで座っている。1人はチサ。そしてもう1人は、僕がここに来た目的。
玉木ミサト。彼女の名前は忘れるはずがなかった。
クラスの多くがそれぞれの会話や作業を行っている中で、2人はこちらを見ていた。この頃はまだチサとも親しかった記憶はない。彼女の方が先に気があったのだろうか。そして玉木さんの視線の意味は…?
高松が席に着き、僕も席に着いた。ただでさえ人生初めてのタイムスリップだ。いつも以上に落ち着いていないといけない。
失敗した過去の2月14日について思い出そうとしていたのもあった。自分の立場を再認識し、告白の方法について考えていたのもあった。もちろん、元々いつも話し相手がいなかったこともあった。
だが僕はそのせいで、自分の身に起こった違和感を無視し続けてしまった。たとえば時の流れが速いと感じても、時計が無ければ無視できてしまうように。
人の物差しは人だ。その異変にはっきりと気が付いたのは、4時間目の体育の授業だった。教師にも当てられない国語や数学とは違ったからだ。
授業は準備運動から始まる。
体育委員の掛け声に合わせて、屈伸やジャンプを行う。
おかしい。
前の生徒が膝を曲げて屈む。当然僕も同じように動こうとする。僕の膝が曲がる。その頃には、目前の彼は立ち上がっている。つまり僕がワンテンポずれていることになる。どれだけタイミングを合わせようとしても、何故か少しだけ僕が遅れている。
混乱しながら理由を探した。思い当たるのは1つしかない。タイムマシンの誤差だ。ぼくはタイムマシンの原理を何も知らない。それが公開されているのかどうかも。だが僕の身に起きているのはそれだと確信した。
僕の意識が、僕の感じる情報よりも約1秒早い。
つまり僕が「今」行おうとした動きは、1秒後の動きになるということだ。信じられないが今そうなっている。
準備体操の最後はジャンプだ。僕は思い切って、他の生徒より早く跳ぼうとしてみた。僕の足が地面から離れる。掛け声と一致した瞬間だった。工夫すれば何とかなるようだ。
しかし安心は一瞬で消えた。見ている情報から1秒ずらして連続して跳ぶのは難しい。滞空時間が思ったより長く、まだ空中にいる状態で跳ぼうと足を伸ばしてしまったり、逆な着地してから跳ぶまでの誤差が大きすぎたりした。早い話が無様だった。後ろの方の何人かの抑えるような笑いが聞こえた。
よりによってメインの内容はサッカーだ。出来るはずがない。パスもドリブルも何も出来ない。同じチームの高松がゴール前でゆっくりとパスしてきたが、それもタイミングを合わせられない。足がボールに引っかかり転んだ。
朝と同じような高松の笑いでフォローされる。立ち上がりながら横にある女子のコートを見た。 玉木さんと目が合い、逸らされた。
正に最悪のタイミングだ。
待ち望んでいた授業終了のチャイムが鳴った。
教室までの廊下で、僕の前に高松や男女6、7人がいた。後ろからその姿を見る。男は全員、短い靴下に少し腰から下がったズボンといった着こなしだ。裾は鍛えられた二の腕を見せるように捲られている。女子の膝上まである靴下は彼女たちの細い足を際立てていた。上着は少し余裕があるようになっている。自分の靴下が、その間をとったような中途半端な長さであることを初めて意識した。
気が付けば彼らに近付きすぎてしまっていたようだ。先に高松から声をかけられた。
「おう斎藤、お疲れ」
いつもの部活の挨拶なのだろう。挨拶の便利さが分かったのも社会人になってからだった。
1秒、2秒、間が空く。
1秒は突然高松に話しかけられて何を言うべきか焦ったから。もう1秒はタイムマシンの誤差のせいだ。高校生の会話で2秒の詰まりは長い。他の男子は既に鬱陶しそうに僕を見ている。
「高松くん、今日の僕、変じゃなかった?」
笑い声がした。高松のものではなく、高松の周囲にいた男女全員だ。
「お前、斎藤!いつも変じゃねぇか」
「今日コケてたでしょ?ウケた」
「ヤバ~い」
何も知らないくせに。僕に起こった誤差も。そもそもお前たちが生まれた時から手にした見た目、要領の良さ、コミュニケーション能力、それら全ての大きさも。うるさい。
うるさい。
「…うるさい」
しまったと思ったときには遅かった。そこにいた全員が黙った。高松がまた口元だけで笑いながら場を取りなそうとしたが、僕は走って階段を上った。上ろうとして、また転んだ。1秒の誤差は大きすぎた。今度は笑い声は聞こえなかった。
一段ずつしっかりと階段を上がっていると、下にいる彼らの声が聞こえてきた。
「何だよ、せっかくいじってやってんのに」
「斎藤くんって本当に何考えてるか分かんないよね」
「あんなだから1人なんだろ」
もうどうでもよかった。だがその中に混じった1つの声に振り向いた。
「高松くん、いっつも斎藤くんに優しくしてあげてるよね。えらいよ」
その声を忘れるはずがなかった。聞き逃すはずもなかった。
あの集団の中に、 玉木さんがいた。
体操服から制服に着替えた。昼休みになった。
他の奴らが弁当を食べるときに集まるいつもの数人組で固まる中、僕だけ1人その場で食べ始めた。いじめが無いのがこの学校のいいところだった。
高松が弁当を持ってこちらへ近付いてくる。
僕の目を見て言った。
「斎藤、頼むよ…」
ため息をつくと僕の隣を通り過ぎ、彼は昼に一緒にいたメンバーの元へ向かった。
50年の時は容易く人を変える。
僕はもう、クラスという集団の中で彼らの賢さを十分に理解できるようになっていた。
「いつも変じゃねぇか」…その通りだ。僕はいつも変だった。実際に高校生のとき、今日のように彼らとの差を広げてしまったこともあった気がする。もしかしたらその日は2月14日ですらあったかも知れない。つまりタイムスリップして、その上1秒の誤差の中で行動して、過去の僕の行動と何も違ったことはしていないということだ。
過去の僕は今の僕より1秒分も不器用だった。それが全てだ。
そして過去の僕は、玉木さんに対して脈があると思っていた。今なら分かる。とんでもない勘違いだ。彼女が気になっているのは僕でなく高松だ。
最早目的の告白をする気分ですらなかった。現代に戻って早くチサに会いたかった。だがこの後僕が彼女と結婚するためには、過去を変えてはならない。未来に影響を出すような行動は避けなければならない。
僕はあのときと同じように玉木さんへの告白を失敗しなければならなかった。
部活動が終わった。
僕は吹奏楽部だったが、1秒の誤差に関してはなんとか誤魔化せた。
5、6時間目の授業中に、誤差を予想した上でタイミングを合わせられるように練習したからだ。足でリズムをとったため、他人からは貧乏揺すりをしているように見えただろう。だが昔の僕は貧乏揺すりが癖だったので、いつも通りではあったはずだ。周囲の迷惑そうな目に、学生の頃は気付かなかったのだ。
部活を終えた生徒は一斉に校門へ向かう。その中に玉木さんもいることを僕は知っている。彼女がどの辺りにいたかも覚えている。
玉木さんは手芸部だった。確か下駄箱のあたりに先回りすれば彼女に会えたはずだ。
登下校用の革靴に履き替えたとき、やってくる彼女の姿が目に入った。他に女子が2人いる。
靴を履いた彼女に声をかけた。
「玉木さん、ちょっといいかな」
彼女は作り物とは思えない笑顔で「少しなら」と微笑む。他の2人は僕から避けるように玉木さんを置いて校舎を出る。
全て昔と同じだ。
「あの、実は…」
ここから何も言えずに14秒が経つ。彼女は夕焼けに染まったガラス窓を見ながら僕の口が開くのを待つ。チョコの入った左のポケットに手を入れる。取り出すと同時に遠くのカラスが鳴く。
それから僕は、午後の授業での努力を無駄にした。
或いは、正確に、更に1秒言葉に詰まった。
僕が口を開けた瞬間、校内放送用のスピーカーがノイズを立てる。告白は完全下校十分前のチャイムに塗り潰される。
チャイムが鳴り終わる。彼女は聞こえないふりをして笑う。
「ごめん、私、もう行くね」
去って行く彼女を追うように一歩ずつ歩く。もちろん追いつかないことも、本当は追いつこうとしていないことも分かっている。
そして昇降口のドアに足を引っ掛けて転ぶ。
ああ、やっぱり最悪のバレンタインだった。
午後5時30分。もうすぐ現代に戻ることになる。
告白した今日の後のことをあまり覚えていない。失敗の衝撃が大きすぎたからだと思う。
だが恐らくは、いつも通り家に帰っただろう。定期を使っていつもの電車、いつも使っていた一番後ろの車両に乗った。
席はそれなりに空いていて、多分その日と同じように適当に座って、その日とは別の女性のことを考えた。
前の車両からのドアが開いた。僕の考えていた女性がやってきて、言った。
「そこ、座ってもいい?」
「もちろん、佐藤さん」
彼女の下の名前はチサと言う。
彼女が最初に話して来たのはSFについてだった。
「知ってる?タイムスリップものって、過去を変えられるタイプと、あらかじめ変えてある前提で伏線が張られてるタイプに分けられるの」
「普通」なら、いきなり何だと思うかも知れない。だけど僕たちはお互いに間が悪くて、お互いに中身のない楽しい話なんて提供できなくて、だからこそ話が弾んだ。
「それより、こんな実験があるんだ。被験者の腕に電流を流して、その被験者が自分の意思で腕を動かしたと思ったか調べるんだけど…」
僕も脈絡のない下らない話を続けた。
チサが降りる1つ前の駅になったとき、彼女はカバンからチョコを取り出した。
「これ、もし良かったら貰ってくれる?」
それは高校生が少し見栄を張って買うようなチョコだった。僕が玉木さんに渡せなかったのと同じものだ。「それならお礼に」と、僕もポケットから取り出して渡した。
チサはクスクスと笑った。その顔を見ようとしたとき、僕の意識は現代に呼び起こされた。
狭い暗闇の中にいた。
すぐ横に唯一光るものがあった。タッチパネルだ。押すと蓋が開いて無機質な天井が見えた。
頭と股間の装置を外した。下の方は、何だか下半身ごと丸洗いされたような感覚だった。
タイムマシンから出ると、始めに服を脱いで入れたカゴを見つけた。服は洗濯された上で綺麗に折りたたまれていた。
その部屋を出るとき、看護師からタイムマシンの記念チケットを渡された。要らないと断ったが、どちらにしろ個人で処理をしてくれと言われた。
病院から出ると、何となくチケットを見た。流行りのキャラクターがプリントされており、「変わらない過去なんて無い!」との吹き出しが付いていた。
「変えられない」の間違いじゃないのか。どちらにしろ病院には不似合いな記念品だと思う。そもそも、どうしてタイムマシンが設置されているのが病院なんだろうか?
そんな考えが頭に浮かんだが、すぐに消えた。
今はどうでもいい。家に帰って、同じ未来を歩けたか確かめなければならない。
「ただいま」
鍵は開いていた。だが返事がない。
「…ただいま」
少し大きな声で繰り返した。やはり返事はない。先に靴を脱ごうとした。足でもう一方のかかとを踏む。焦っているのか上手く脱げず、しゃがみこんで靴紐を解いた。
誰かの足音が廊下から近づいてきた。ちょうど靴が脱げたとき、声がした。
「あら、お帰りなさい」
顔を上げなくても声の主が分かった。何十年も聞き慣れた声だったからだ。顔を上げないまま言った。
「…なぁ、チサ。これからもよろしくな」
しばらくしてから顔を上げた。
「どうしたの?急に」
「何も無いよ。ただ僕たちが付き合ったとき、周りから『お似合いカップル』って笑われたじゃないか。あれは別に皮肉でもなかったのかなと思ったんだ。それを急に思い出した」
彼女は俯いて笑った。
50年の付き合いは大きい。僕はその笑っているのが口だけだと判断できるようになっていた。
問い詰めるわけでもなく、僕の直感を確かめるように聞いた。
「何か隠してるのか?」
彼女はぽつりぽつりと話し始めた。
「高校2年生のときのバレンタインの日のことなんだけど、私たちが会話したの、覚えてる?」
僕は頷いた。
「多分私たちが一気に近づいたときだったでしょ。実はあの日、あなたと話す前に失恋したの。同じ電車の、前の車両にいた高松くんに」
僕は何も言わなかった。
「それでね…あなたはこれを許してくれる?」
彼女はポケットから一枚の紙を取り出した。
タイムマシンの記念チケットだった。
僕はやはり何も言わなかった。何も言わず、下を向きながら自分のポケットから同じものを取り出した。
「それ、どういうこと?」
彼女の声は冷たかった。慎重に窺うようにしてチサの顔を見た。
見ると、僕にははっきりわかった。
チサは笑っていた。
いいなと思ったら応援しよう!