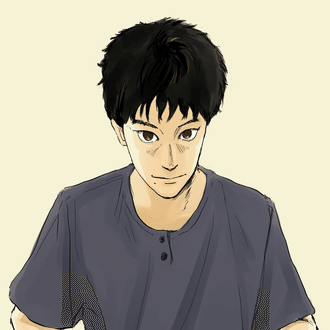【日記】屋上の賞味期限
高校生になれば、屋上には自由に出入り出来ると思っていた。ジャンプ漫画の中で何度も読んだ。だが現実は甘くはなく、立ち入る機会すら与えられなかった。
誰もが夢見て諦める。高校の屋上とはそういう場所ではないだろうか。
僕は今日、その屋上に登ることが出来た。これはその記録。苦難と勇気の物語である。
屋上に入る難しさを知ったのは1年の終わりの頃だったと思う。
体育の授業に一回分の空きが出来て、その時間をクラスごとに自由に使っていいことになった。場所も、教室の他にグラウンドや体育館の使用も許可された。ただ多くのクラスが密集すると体育館などは使いにくくなるため、前もって担当の先生に報告せよとのことだった。
僕のいたクラスは教室でフルーツバスケットをすることになった。係の仕事で、僕がその報告をしに行った。そのときついでに先生に聞いてみた。
「ちなみに、何してもいいなら“屋上で昼寝”とかもアリなんですか?」
先生の答えは厳しかった。
「皆が納得するなら昼寝自体はアリやけど、生徒に屋上へ立ち入らせる許可は絶対出されへんわ」
事故が起きた際の責任問題を考えれば、それは当然の答えだった。不満は何も感じなかったが、漠然と屋上へ行きたいという思いが心に芽生えた。「昼寝自体はアリ」なのか、とも思った。
2年の春から夏にかけては、屋上へ行きたくて仕方がなかった。
今思えば現実逃避の一種だったのかも知れない。意味もなく学校を休んで歩き回りたくなる衝動に近い。僕のその思いはたまたま屋上へ向いていた。
とはいえその時期はかなり本気だった。屋上へ行く方法を真面目に考え、そのための準備を進めていた。
たとえば、屋上に通じるドアは3ヶ所ある。そのうち1つは教室前の廊下にあるが、ノブすら回せないように固定されており、恐らくドアとして使えない。残りの2ヶ所は別々の館、その最上階にある。屋上へ続く階段には「立入禁止」の文字があるが、物理的な妨げは何も無い。その階段を登るとドアがあり、その先には屋上が広がっている。
つまりそのドアさえ開けられれば、屋上へ行けるというわけだ。ドアの前には基本的に人は来ないが、当然音がすれば気づいてしまう。だが学校の防犯対策はほぼ無いに等しく(職員室前にあるSECOMの端末が防火用のみであるのを確認したり、今思えば馬鹿馬鹿しいが丁寧に下調べを行なっていた)、夜のうちに校内に入ることは出来る。探偵小説に感化された友人の「窓の“さん”にゴム片を挟んで鍵が閉まらなくする」作戦は失敗したらしい。だが校舎の窓も高いところのカギには埃がかかっており、昼のうちに開けておいても誰も気づかれそうになかった。
問題はピッキングだった。ドアの鍵穴を見てみたところ、ディスクシリンダー錠と呼ばれる旧式のもので、比較的簡単に解錠できるらしい。しかし「簡単」という表現も相対的なものでしかなく、素人にはそれなりの努力が必要なようだった。
道具を買うにも数千円を投資することになる。中学の頃の友人が鍵師になるのを目指していたため、この程度の鍵ならピッキングが出来たことを思い出したりもした。しかし数年ぶりに会って「屋上に行きたいからピッキングだけ手伝ってくれ」と言うのも気が引けた。
最後の最後で実行には移せないまま月日は流れていった。
2年の終わりからは、今度は屋上への思いが冷めてきた。
完全に興味が失せたわけではないが、「そこまで苦労して行かなくても」といった気持ちになっていった。理由は、単純に他のことに興味が分散したからだろう。駅伝のシーズンで部活にも真剣になっていたし、小説などの作品も以前より高頻度で作るようになっていた。
矛盾しているようだが、この時期に思っていたのは「屋上へ行くなら高校生のうちに」ということだった。屋上へ行きたい衝動は、恐らく高校生活での諸々のストレスから生まれたものだ。だから大学生になってゆっくりピッキング技術を学んで屋上に登ることが出来たとしても、それほど感動出来ないだろうという気持ちがあった。
欲しいものには「賞味期限」がある。欲しくなくなった後に得ることが出来ても、それは「昔欲しかったもの」でしかない。最大限の鮮度で感動を得たいなら、欲しいものは今掴み取らなければならない。
今ですら、2年の中旬よりは願望が薄れてきている。屋上へ行けないまま卒業を迎えたとしても特に残念には思わないだろう。ただいくらかの後悔は生じるかも知れない。屋上への思いは、行こうとする意識から後悔への不安に姿を変えて頭の中に残り続けていた。
そして高校3年の夏休み、今日(8月2日)を迎える。
部活終了直後、合宿に備えて配るプリントを数人で分類しているときだった。屋上の上に3人ほどの人影が見えた。それ自体は珍しくはない。ソーラーパネルの設置など、作業員が立ち入ることはよくあった。だが今日屋上の上にいる何人かは、いつもの灰色の作業服と違い、白いシャツを着ていた。周囲を見回してみると、屋上の真下にも数人の生徒と先生がいた。壁に沿わせて大きな布を掲げようとしているようだ。それが体育祭で使う旗だと分かったとき、屋上にいるのが生徒会だと気付いた。
別に何か策があったわけではない。生徒が屋上に入る先例が出来たなら、今頼めば僕も入らせてもらえるかも知れない。安直にそう思った。
持っていたプリントを近くにいた女の子に預け、急いで制服に着替えた。グラウンドを通り抜け、屋上の真下にいる2人の先生のところへ駆け寄った。先生の1人は、僕の学年の主任だった。ソフトボール部の顧問でもある。部活の監督をしているついでに作業を眺めていたのだろう。もう1人は今年から入ってきた別の学年担当の先生で、話したことは一度もなかった。まず主任の方に話しかけた。
「ぼくも作業を手伝うんで、屋上行ってもいいですか?」
主任は苦笑いをして、「おれは担当ちゃうから」ともう1人の先生の方に首を振った。その生徒会担当らしい先生に同じように問うと、最初に「お前落ち着け。そもそもお前誰や」と言われた。確かにその通りだった。
「生徒会と全く関係ないですけど、兼ねてから屋上に行きたいと思ってたんで、手伝う形でいいんで登りたいんですけど…」
説明を聞いてもらえたのかよく分からないまま、一先ず僕も下から作業を眺めることになった。よく見ると下の方にも生徒会役員と思われる数人の生徒がいる。上にいる数人と事務員が、旗を引き上げる作業をしているようだ。
屋上に登る生徒を遠目に見ていると何故か腹が立ってきた。中学の頃で自粛していた貧乏ゆすりが酷かった。
しばらくして、屋上から事務の方が顔を出して叫んだ。
「思ったより重いから、野郎は何人か上がってきてくれ」
担当の先生を見た。一瞬で許可が降り、屋上まで疾走することになった。
下駄箱のあたりで帰ろうとしている部活の後輩と出会った。彼曰く僕は笑いながら走っていたらしい。屋上に誘ったが断られた。屋上よりも一本の電車を優先する人種もいる。
屋上には僕を合わせて6人の男子生徒、1人の女子生徒と、先ほどの事務の方がいた。懐の広い生徒会役員達は僕を単純に労働力としてみなしてくれたらしく、無駄な説明もなく馴染めた。3本あるロープを2人ずつ持って引き上げたり、旗の弛み具合を見ながら大会当日に増やすロープの数を相談したりしていた。その場で唯一手帳を携帯していた僕がメモ係としても働くことになった。
もちろん目先はロープを持つ手や旗ではなく、いつもより遠い地平線にあった。近くのAEONの屋上が見えた。部活で野外走のとき、数十分かけて走るコースが一目で見渡せた。空は近く、街は小さく見えた。先ほどまで自分がいた陸上部の方に手を振ったりして遊んだ。後半になると余裕が出てきて、その棟の最上階である4階で練習している吹奏楽部に指をさして「おいおいおい、何や低いところに人がおるでぇ」などと言って、その場のメンバーと笑い合ったりした。5階の上が別次元の高さに感じた。
作業が終わるとゆっくり屋上を一周して、とりあえず目下の世界に「ありがとう」と叫んだ。少なくとも「バカヤロー」とかよりは良いと思った。それから生徒会役員にも最大限の感謝を伝えた。生徒会の活動とはいえ、屋上から旗を吊るすのは今年が初めてだという。自分の運の良さにも感謝した。
階段を下りて担当の先生に「もう高校生活の悔いはありません」と言うと、「まだこれからやろうが」と返された。この人の言うことは大体その通りだった。
「そこまで苦労して行かなくても」と思っていた屋上だったが、名前も知らない先生に頼み込んで行く程度の価値は十分にあった。
1つ乗り越えると、もう1つ何かやりたくなるのが人の性らしい。今は「学校をサボって遠出」と「学校の夜のプールで泳ぐ」がしたい。
生徒会のイベントで行ってくれないだろうか。
おわり
いいなと思ったら応援しよう!