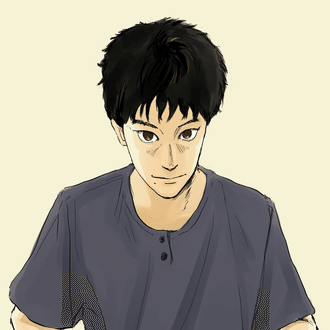『フシのボタン(1万字)』
【男 Ⅰ】
ちょうどよかった。
癌の告知をされたときは、そう思った。
今のおれにあるものを考えた。妻と娘がいた。大学を出てから働き続けている職場があった。だが妻子とは五年前から別居している。理由ももう忘れてしまった。きっと小さなすれ違いだろう。連絡の取り合いすらほぼ無く、家族というよりは血の繋がった他人に近かった。仕事には真面目に取り組んでいたが、それも真面目であるだけで、決して積極的ではない。生計を立てるため、あるいは仕送りという形だけでも家族とつながるために、しがみついていたにすぎない。
そんなおれにとって、もはや手術でも取り出せないという癌は、惰性で続くゲームの終わりに相応しいリセットボタンだった。苦しんで延命することもないと思い、抗癌剤治療は断った。
入院から一ヶ月。「大事なことなので」と、主治医は妻をおれの病室へ呼び出した。医者以外に人が来るのは初めてだ。
「久しぶりだな」
妻に声をかけたが、こちらを見ただけだった。この前顔を合わせたのは正月だから、もう三カ月も会っていなかったことになる。
「お話というのは?」
妻は、おれのベッドの隣に座っている医者に聞いた。
「はい。二つ、お伝えしたいことがあります。大変申し上げにくいのですが…」
「余命宣告、とかかな?」
おれの方から聞いた。事務連絡は短い方がいい。
「…はい。三ヶ月ほどかと」
驚きはしなかった。少し長いとすら感じた。だが、その後に続いた、「二つ目」の連絡は、おれの予想し得るものではなかった。
「実は、まだ検証段階ですが、『不死の薬』とも呼べる薬が出来ているんです。被験者になってみませんか?」
おれも妻も、気の抜けた声を出した。二人で同じ反応をしたのはいつぶりだろうか。ともかく簡単には受け入れられない。少し間をおいた後、医者は説明を続けた。
彼が話すにはこういうことだった。先日、延命効果のみにおいて完璧を誇る薬が完成した。それが不死の薬だ。投薬している期間は病気や寿命で死ぬことはなく、いつも通り生活できる。ただ薬の効果はあくまで「死なないこと」であり、「病気を治すこと」ではない。まだ検証中であることや倫理的な問題もあることから、おれのように治療の余地がない患者にだけ試験的な投薬を行っている。
「もちろん『不死の薬』の存在が知れ渡れば、不正に求めようとする人や混乱が発生しかねません。ですからこのことはご家族以外、他言無用でお願いします」
「なるほど。聞いたことも無いわけだ。だが、それはつまりおれの場合、癌の痛みに苦しみながら生き続ける事になるんだろ?…生き地獄じゃないか」
「そういえば投薬方法をお伝えしていませんでした。『不死の薬』は点滴で投薬するのですが、それと一緒にボタンをお渡しします。そのボタンを面会時間外に押すと、点滴と連動して次の一日分だけ投薬される仕組みです」
「つまり明日生きるかどうかを選べるというわけか」
「はい。面会時間中に押しても反応しないのは、本人以外の意思でボタンが押されることを防ぐためです。もちろんボタンを押さなかったからと言って、翌日寿命がくるとは限りませんが」
おれはその不死の薬に興味を持ち始めていた。死ぬ間際になって、未知の科学に惹かれたのかも知れない。それとも自分の意思で死期を選択できるという自由さに憧れたのか。妻はおれを見ると、「あなたが決めて」とだけ言った。
「これまで通り、痛みを和らげるためのモルヒネなどの投薬にも保険は適用されます。『不死の薬』も試験薬ですので、治療費は変わりません」
デメリットがあるわけでもなさそうだ。おれは不死の薬の投薬を決めた。
【少女 Ⅰ】
「あの人の余命を言われたわ。あと三ヶ月って」
家計簿をつけながら、お母さんはそう告げた。何と返したらよいか分からなかった私は、「そう」とだけ言った。
血の繋がった父親とはいえ、会う頻度は近所に住む叔父の半分にも満たない。余命三ヶ月と言われても、実感がわかなかった。父の死にではない。その存在にだ。
「それとね、よくは分からないけど不死の薬っていうのがあって…」
お母さんは続けようとしたが、もう家を出る時間だった。
「ごめん、お母さん。陸上部の朝練があるから。帰ってきたら…あ、仕事、今日は遅番か。今度聞くから」
伝えると、鞄を持って部屋を出た。玄関に一番近いドアの前で足が止まる。父がかつて書斎に使っていた部屋だ。父の姿を思い出そうとしたが、頭に浮かぶのはここでパソコンに向かう背中くらいだった。立ち止まっていると床と足とが離れなくなってしまいそうで、私は頭を振ると早足で家を出た。
今日の朝もいつもと変わらない景色だった。花に水をやる向かいのおばさん。川沿いに生い茂る草。「神様は乗り越えられる試練しかお与えになりません」と声を上げる、駅前の宗教団体。全ていつも通り…そのことが何故か、私には変に思えた。
学校に着いてからもそれは同じで、決まった時間になると顧問のミーティングで練習が始まった。毎日変わらない掛け声とアップ動作を済ませると、次はリレーメンバーでのバトン練習になる。
いつもと変わらない。ただ私だけがおかしかった。楽なスピードのはずなのに、どうしても足が回らない。さすがにメンバーも気付いたようで、バトン練習の後で声をかけられた。
「どうしたの?全然いつもと違うじゃん。地区予選までもう一ヶ月なんだから…」
そのとき、私はまともに立てないほどの孤独に襲われて、「ごめん、調子悪くて」と言うとすぐトイレに駆け込んだ。
たくさんの感情がごちゃまぜになっていた。悲しかったし、苛立たしかったし、何より寂しかった。まるで世界の残酷な真実を私だけが知っているようだった。いつも通りの日常は当たり前なんかじゃない。
声を殺して泣いた。しばらくそうした後、久しぶりにその言葉を口にした。心の中で思っていただけのつもりだったのに、気が付けば声に出していた。
「お父さん…」
【医者 Ⅰ】
パソコンにデータを打ち込んでいると、一人の看護士が覗き込んできた。彼女はぼくと同じ時期に医療の世界へ踏み込んだ、いわば同期だ。長い付き合いだが、この頃、何かと話しかけてくるようになった。
「それ、今『不死の薬』を投薬してる患者さんの?」
「ああ。ボタンが押された回数をグラフにしていた」
「今のところ、合計回数は?」
「…一回だ。三日前に一回。開始から二週間も経つのに」
「あの人、毎日退屈そうにしてるものね。生きたい理由も特にないのよ、きっと。あ、でも三日前って、初めて奥さんと娘さんが二人で面会しにきた日よ。ちょうど私が部屋の掃除をしていたときだから覚えてる」
ならこの一回は、娘と会ってもう少し生きたいと思ったということなのだろうか。
「面会って言っても、入院費の支払いとか、奥さんと事務的な話をしてただけよ。娘さんはずっと端っこでスマホ触ってた。まさに反抗期って感じでね」
ぼくはため息をつく。
「じゃあこの一回も気まぐれに近いのか。君はどう思う?この薬…」
今度は彼女がため息をついた。
「私が何を言っても信じるんでしょ?『不死の薬』を。…あなたが作ったんだものね」
【男 Ⅱ】
あの日、なぜボタンを押したのだろう。何も考えるべきことがない中で、ときどきそう
思った。
ボタンを押した翌日、少し体が軽く感じた。それが気に入らなかった。不死の薬の効果は延命だけだったはずだ。だとしたらあの感覚は、薬よりも気持ちによるものである可能性が高い。ボタンを押したことで、おれの中に深く沈んでいた、生への執着が肉体の方へ浮かび上がってきたのではないか。
その考えを認めたくない一心で、今ではボタンもベッドの下に落としていた。
誰かが部屋の扉をノックした。入ってきたのは妻と娘だった。二人で来るのは二回目になる。この前は二週間ほど前だったか。
今回も、妻と生活費について話した。まだおれが働いていたころの金があるので、入院費は心配しなくていいという。一通りの会話が終わると、前と同じ心地悪い沈黙が流れた。
「じゃあ、帰るわね」
妻が言った。携帯を見ていた娘もその声に反応し、壁に預けていた背中を離す。おれは歩いていく二人の後ろ姿をただ見つめた。
一瞬、自分がデパートにいる錯覚に陥った。家のドアを開けると、その日五歳になる娘が駆け寄ってくる。この子、あなたの帰りをずっと待っていたのよ。あとからやってきた妻がそう言って微笑む。おれの疲労感は消え去り、久しぶりの外食を提案する。車内のミラーから、夕日で真っ赤に照らされた娘の笑顔を見る。おかしくもないのに、おれの口にも笑みが浮かぶ。楽園にでも行くかのように、デパートにあるチェーン店へ向かう。そんな日の帰りを思い出した。
二人はもう手をつないで歩いたりはしない。おれにはもう、その背中にかつての面影を重ねるのさえ容易ではなかった。時の流れは、あの小さな宝物をどこかの少女へと変えてしまった。
娘の名前を口にした。
意図したわけではない。それは唇からこぼれるように、自然な出来事だった。娘は怪しむような表情でおれに顔だけを向けた。だが、彼女以上におれが困惑していた。どうして声をかけたのかもわからない。今は言葉の続きを探すのに必死だった。
「…学校は、上手くいっているのか」
娘は出口の方へ歩き出す。その背中から、「うん」とだけ聞こえた。病室のドアが閉まり、静けさが部屋を満たした。
なんであんなことを言った?後悔に似た感情が、頭の中を占領していた。もう死と隣合わせの体だというのに、心は片思いの女の子に話しかけた後の少年のようだった。自分の娘とはいえ、この前まともに会話をしたのもいつだったか。いきなり名前を呼んで不快だっただろうか。仮にも親のくせに、誰にでも言える平凡な質問をしたことに辟易しただろうか。考えれば考えるほど気恥ずかしかった。彼女にもう一度会って、今日の言い訳をしたかった。その言い訳すら上手くいくはずもないことは分かっている。そもそも言うべきことなど何もないのだから。それでもおれは、これで最後になることを自分でも驚くほどに恐れていた。
次に彼女に会うまでなら、生きていてもいいかも知れない。死ぬのはそれからでも遅くない。
おれは不死の薬の点滴から繋がっているコードを手繰り、そのボタンを枕元に置いた。
【少女 Ⅱ】
私は父の病室にいる。この前から一週間ぶり、三回目のお見舞いだった。ここに来てから、「反抗期」という言葉の意味が分かるようになった。今日こそ何か話そう。病室の前でそう決心したはずなのに、父を見ると決意はどこかへ吹き飛んでしまう。いつも扉の向こうにいるのは、私の知らない無愛想な私だけだった。彼女は父と話すことも、隣で母との会話を聞いていることもできない。前と同じように壁にもたれ、携帯を眺めていた。この前は学校の様子を尋ねてきてくれたけど、そっけない返事しかできなかった。
お母さんとお父さんは、前と同じように淡々と会話していた。どうやらお金絡みの話らしい。今日はいつもより長い。会話が終わったように見えても、すぐにお父さんが何か別のことを話しかけているみたいだ。ときどきこちらを向いているように感じるのは、私の気のせいだろうか。顔を上げると、お父さんと目があってしまった。私は慌てて、また携帯に目を落とす。
このままではいけない。結局のところ、空白の期間があったって親は親だ。ここで何もやり取りせず帰ることは出来る。でもそれでは、父のことがより一層気にかかってしまう。それは心だけでなく、体にもよくない影響を及ぼす。もちろん、三週間後にある県大会にも。数日前の地区予選はなんとか通過できたけど、いい調子とはとても言えなかった。私はリレーメンバーの一員だ。皆に迷惑をかけるわけにはいかない。
恐る恐る、もう一度顔を上げてみた。数秒と置かず、また父と目が合う。父は、今度は明らかに私を見ようとこちらを向いていた。
「この前の話なんだけどな…」
それが私への言葉だと気付くのに時間がかかった。この前の話?学校について聞いてきてくれたことだろうか。冷静に記憶をたどろうにも、緊張して頭が回らない。
「どうでもいいけどさ、」
咄嗟に言葉をつなごうとして、私の方から話しかけた。
「どうでもいいけど、ちゃんとボタン押してるの?」
【医者 Ⅱ】
「なあ、先生。今からでも抗癌剤治療ってできないのか」
『不死の薬』投薬開始から一ヶ月半。被験者の回診をしていると、そう聞かれた。
「そうですね…もう癌の回復は見込めません。試してみても、苦しむだけでしょうから」
「ああ。本当は、聞かなくても分かっていたんだ。だが最近不安でな。先生と同期だという看護士に言われた。生き続けるのは幸せか、と」
「…彼女がそんなことを?」
男は頷いた。
「それに、いつまでも妻に頼るわけにもいかないしな」
「……そう言えば、最近は奥さんと娘さん、頻繁にいらっしゃっていますね。ボタンを毎日押すようになったのも、それが理由ですか?」
聞くと、男は黙ってしまった。余命宣告すら動じなかった人だ。今になって生きようとし出すことは、彼にとっては恥なのかも知れない。だが、やがてはっきりと答えた。
「そうだ。この目で娘の成長を見たくなってしまった。今まで仕送りでしかつながりを持とうとしなかった、このおれが」
男はそう言い、自嘲気味に笑った。
「素晴らしいことじゃないですか。生きましょうよ。…前を向いて生きましょう!」
だが、男の表情はむしろ暗くなった。
「今度、娘が陸上で県大会に出るらしい。リレー種目だけだがな。おれも、長距離だが陸上をやっていた。先生は何かスポーツは?」
「ぼくですか?…いえ、特に部活には入っていませんでしたから」
「陸上は…もちろん陸上に限った事でもないだろうが、おれはそれしか知らないからな。陸上は、強いほど苦しいんだ。同レベルの仲間が減っていく孤独もあるが、それだけじゃない。終わりの見えない苦痛だ。五千メートルを十六分で走れたら、次は十五分半。それもできたら、今度は十五分より速く…目標を達成すればするほど、窒息していく感じだ」
「あの、失礼ですが何の…」
「今のおれの話だよ。最初は、苦しまずに死ねればそれでよかった。悩み事なんて、無駄にした人生への後悔だけだった。それなのに、妻と会い、娘と話したいと悩むようになった。すぐにその望みも叶う。今では……娘の大会を見に行けないことが、この上なく辛い…」
最後は涙混じりの声になり、それから何も話さなかった。彼は最初から、自分の入院が家計に負担をかけることを気にしていた。そして今、生きようとすることに罪の意識を抱いている。
ぼくは男の腕につながっている『不死の薬』のチューブを目で追う。そして男を問い詰めたい衝動に駆られた。
家族と疎遠のまま死ねば幸せでしたか?それでも毎日ボタンを押すのは何故ですか?
【男 Ⅲ】
体がひどくだるい。不死の薬の効果は延命だけ。進行こそしないものの、癌は回復するわけではない。痛みにも慣れてきたつもりだったが、最近また苦しくなっていた。心の迷いが原因だろうか。家族に負担をかけ続ける延命など、快く受け入れられるわけはない。だが、そう思っているはずなのに、一日の終わりにはボタンを押してしまう。意識が遠のく。このまま明日まで眠れば、楽になれるのだろうか。
「お父さん…お父さん!」
目を開けると娘と妻がいた。娘の声で頭がはっきりした。「おとうさん。」その音はおれが家族と過ごし、働いていた頃から、おれを生に結び付けようとする。
「大丈夫?聞いてた?私の話…」
「ん、ああ。これからも陸上は続けるんだったよな」
「うん。やっぱり、思いっ切り走るのが気持よくて」
そう。確か、昨日終わった県大会の話だった。
「その様子だと、いいタイムで走れたみたいだな」
「リレーはチームのベストタイムだった。決勝の中では最下位だったけどね。でも今までで一番いい走りだった。私は満足してるよ」
「そうか。…それが一番だな。次のブロック大会に進めた仲間もいるんだろ?新聞で見た」
「一人だけね。男子二百メートルで県二位。凄いでしょ?でも本人は一位の子に負けたのが悔しかったらしくて、皆の見えないところで泣いてた。私たち女子のリレーよりずっといい順位なのにね」
おれはこの前の医者との会話を思い出した。無意識に表情が曇ってしまったのだろう。妻が顔を覗き込んできた。おれは「大丈夫だ。何も問題ない」と言った。
「その二位の奴はちょっとかわいそうだけど、でもその分すごく格好いいし、羨ましい。努力して苦しんでようやく勝って、また努力して…それが楽しいんだよね。きっとあいつが悩むのは、挑戦したいことに向き合えてるからなんだ」
その言葉を聞いて、また目が覚めるような衝撃が体を駆け抜けた。確かにそうだ。諦めていないことにこそ、悩む余地があるのかもしれない。
「…そうだな。おれの主治医にも伝えておくよ」
彼とおれの会話を知らない娘は、「お医者さんには言わなくていいよ」と笑った。その様子が愛おしくて、おれも笑ってしまった。妻は微笑みながら、少し離れて眺めていた。
「あなた。悪いけど、そろそろ仕事だから」
「ああ、忙しいのに悪かった。今日は久しぶりにちゃんと笑った気がする」
「お母さん、もうちょっとここにいてもいい?電車で帰るから」
「お父さんが疲れない程度ならね」
妻が病室を出て、部屋の中にはおれと娘の二人だけになった。
「帰らなくてよかったのか。今年、大学受験だろ?」
「大丈夫。…そういえば、お父さんと進路の話、したことなかったね。実は受験は止めて、来年から働こうかと思ってるんだ」
「何を言ってるんだ?だって大学でも陸上を続けるって…」
「大学で、とは言ってない。グラウンドさえあればどこででも走れるよ。元々私の高校ってそんなに進学校じゃないし、大学に行った先輩たちだって遊んでるだけだしさ」
「だからって…」
「今更親みたいに口出しするの?」
静かな声だった。だが、それが一層おれの心に堪えた。
「…私、夢ってほどじゃないけど、ずっと前から思ってた理想のイメージがあるんだよね。お母さんだけじゃなく私も働いて、それで家にお父さんもいるの。それで、公式の大会には出られないけど、記録会を二人に応援してもらう。平凡だけどさ」
何も答えなかった。本当は今すぐ娘を抱き締めたかった。だが親として、取るべき態度はそれではないと知っていた。
「今すぐ出て行け」
娘は明らかに動揺した表情を見せた。
「えっ?…」
「出て行きなさい。そしてもう来るな」
「ちょっとお父さん?今更親みたいに、とか言ったのは悪かったって!」
「今すぐ!」
娘はやがて荷物をまとめ、何も言わず部屋を出て行った。
どうやらおれの存在は、思っていた以上に家族に迷惑をかけていたらしい。決断の時が迫られていた。枕元にある、もう手垢で汚れたボタンを手に取った。こんなものが手の届く所にあるから、おれは生に縋ってしまう。そして、今度はそれとは違うボタン、最初からそこにあった、ナースコールを押した。
一分とかからず、看護士がやってきた。おれの言うことは決まっていた。「不死の薬の使用をやめたい」それですべて解決するはずだ。だがいざ言おうとすると、恐怖から喉が震えた。最早おれにとっては、自殺に近い行為だ。
「どうかされたんですか?」
言わなくては。
「…いや、すまない。間違って押してしまった」
看護士は首をかしげ、すぐ帰っていった。頭をよぎったのは、「喧嘩したままおれが死ねば、娘は一生後悔するのではないか」ということだった。自分でも分かった。ただの詭弁だ。娘を追い返した時の覚悟とまるで逆じゃないか。
知らなかった。幸せを失うのが、これほど恐ろしいことだとは。
【少女 Ⅲ】
私は今、電車で病院へ向かっている。今回で、お父さんに来るなと言われてから十回目のお見舞いになる。
喧嘩して以降も、私は二、三日に一回の頻度で病室を訪ね続けていた。一人で行って、最近あったことを話した。お父さんは返事すらしなかったけど、聞いているという実感はあった。
それでも無視はつらい。さすがに、二回ほどのお見舞いでやる気はしぼんでいた。そんなとき、病室前でお父さんの担当医と看護士に出会った。二人で何か話していたけど、勇気を出して気になっていたことを聞いた。
「先生、父は、今もあのボタンを押しているんですか?」
「ん、ああ。毎日、それも何回も。癌の影響で仕方がないけど、その日ボタンを押したか不安になることがあるらしくてね。他にも、激しい痛みを感じた時にもボタンを押しているようだ。気分の問題とは知っていながら」
「本当ですか」
「もちろん。最近、君にひどいことを言ったとかで、仲直りするまでは死ねないって話していたよ」
隣にいた看護士も言った。
「あなたも、伝えたいことがあるなら急いだ方がいいわ」
お父さんには生きる意志があった。ボタンも押さず、寿命が来るのを待っているわけではなかった。それを聞いて以来、また何度でも来ようと決意した。
変化があったのはこの前、九回目でのこと。その日は私自身にも大きなニュースがあった。
「お父さん、覚えてる?あの県大会で二位になった二百メートルのチームメイトのこと…」
いつも通り、お父さんは何も言わなかった。
「私ね、そいつと…付き合うことになったんだ」
やはりお父さんは何も言わない。ただそれを聞いて、少し下を向いた。それからゆっくりと、袖で目元をぬぐった。私はどうしていいか分からなくなり、「今日はもう帰るね」と言って出口へ向かった。
「待ってくれ」
数十日ぶりに聞いた、お父さんの声だった。
「…悪いな。無様な姿ばかりお前に見せて。何も悲しいわけじゃないんだ」
「お父さん」
「もしおまえが許してくれるなら、また今度来てくれないか。ちゃんと話し合おう。お前にとって、何が幸せか」
今回はお母さんも来ることになっている。最近は仕事を増やしていたけど、何とか都合をつけてくれた。私とは別々に向かう予定だ。もうお母さんは着いているかもしれない。
病院の最寄り駅で降りると、携帯を見た。マナーモードで気付かなかったけど、私が電車に乗っている間、お母さんから何度も着信が来ている。不吉な予感がした。私はすぐに電話をかけた。コール音よりも心臓の音がはっきりと聞こえた。
近くで、いつもの宗教団体の声が聞こえた気がした。「神様は乗り越えられる試練しかお与えになりません」
【医者 Ⅲ】
霊安室に少女がやってきたのは、男が死んで一時間が経った頃だった。冷たくなった男に向き合うと、母親に寄りかかり泣き叫んだ。長い間そうした後、ぼくの姿を認めると非難するように問うた。
「…どうして父は死んだんですか……?ボタンは毎日押しているって…」
その眼差しは真剣そのもの、父への愛があっての力強さだった。
「君のお父さんは、最後まで君たちの幸せを思っていた」
「じゃあどうして!……どうして…」
「…だからこそだ」
彼女はぼくの目の前で泣き崩れた。その様子を見ていた母親が、少女の背にそっと手を置く。そしてぼくを見上げ、丁寧に話しかけた。
「先生、もし可能なら、主人が不死の薬で使っていたボタンを、この子に譲っていただけませんか」
傍にいた同期の看護士もぼくを見た。
「分かりました。ボタンに記録されたデータは消去してからになりますが…」
母親は深く頭を下げて礼を言った。
「あの子には小さい頃の主人との思い出がありません。病院での会話が全てでした…本当にありがとうございます」
仕事部屋へ戻ると、同期の彼女も付いてきてぼくを責めた。
「『不死の薬』がなければ、あの娘に残酷な嘘をつくこともなかった。やっぱり私は反対よ。こんなやり方」
「仕方ないじゃないか。彼が押すことを躊躇っていたのは事実だ。…前から単独で患者に何か話していたらしいが、それも君の考えによるものか? 」
「ええ。やりたいことは生きているうちにやるよう、助言したのよ。不死じゃ死とは向き合えないから」
「……全てを明かしてはいないよな?」
「まさか。あの家族に言えるわけないわ。『不死の薬』の正体がただのビタミン剤だなんて」
そう、『不死の薬』は偽薬だ。「死なない」という効果も嘘。…だが、「生きたいと自覚させる」ことなら出来る。
「君が不死を悪く言えるのは、それが存在しないと知っているからだよ。あの薬は、失われていた夫婦の時間を取り戻した。あのボタンは、離れていた父子をつないだ。…立派な終身医療じゃないか」
ぼくはボタンのメモリーをパソコンへつないだ。男のボタンを押した回数がグラフになって、画面に現れる。「これは幸せなの?」彼女はそう呟いた。
日ごとに高くなっていくその棒グラフは、ぼくには、天国に続く階段のように見えた。
いいなと思ったら応援しよう!