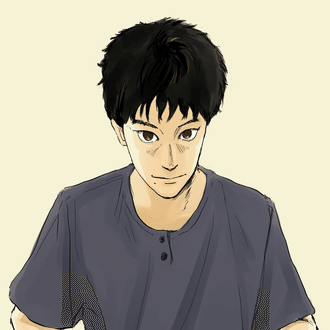『I novel』(星新一風2次創作)
N氏の心の中には、いつも一冊の絵本があった。
昔、保育所で一度だけ読んだ本。主人公の冒険物語だ。
その内容はN氏の小さな世界を無限に広げた。綴られる言葉の1つ1つが、N氏の小さな胸を躍らせた。
それからの彼が経験した劇的な出来事は、全てその本に重ね合わせた。大きな岐路に立ったときは、その本の主人公になりきって選択を下した。
N氏はその六十余年の人生を、そうして歩んできた。特別華やかではなかったが、十分N氏の納得にいくものだった。今年定年退職したN氏には、その老後を費やして成し遂げたいことがあった。
「自分の人生そのものであるあの絵本を、もう一度読むこと」
N氏は、その本の題名を覚えていなかったのだ。
もちろんこれまでも、あの絵本を求めて色々な方法を試みた。
かつてそれを読んだ保育所に行ってみたこともあった。しかし並べてある本の多くは新しいものに変えられており、探し当てることは出来なかった。
インターネットで検索しようとしたこともあった。しかしネットの記事が爆発的に増えた今となっては、関係のないと思われる情報しか見出せなかった。そもそも古い本で、ネット上に記載されていたとも思えない。同じ理由で、周囲の人間は誰もその存在を知らなかった。
今のN氏が試そうとしたのは、それとは全く違う方法だった。
端的に言ってしまえば、それは盗作だ。
自分の記憶を頼りに、あの絵本を出来る限り再現する。それを出版社に持ち込むか、残りの財産を費やして販売する。
あんなにN氏を感動させた絵本だ。N氏は自分に文才があるとは思えなかったが、あの本のコピーが出来たなら、それなりの人気が出ると踏んでいた。本は広まり、多くの人間の目に留まる。そしていつかN氏の求める人間が現れるはずだ。「このN氏の本は、昔出版されたあの絵本の模倣だ」と言う人間が。N氏の人生を支えた、あの絵本の題名を知る人間が。
N氏は人生の中で、その内容を何度も何度も反芻してきた。再現できる自信はあった。
だが、もちろん盗作で印税を得るのは犯罪行為だ。家族を養っていく必要や世間体も考慮すると、今まではそれが出来なかった。
これは残り少ない人生となってこその、N氏の切り札だった。
かくしてN氏はそれを実行に移した。
ところどころ曖昧な部分は、N氏自身の人生を振り返り思い出した。もはやN氏の人生がその本そのものだったのだ。記憶を辿れば、自然とあるべき文字が浮かんできた。
一冊の本として完成させると、出版社に持ち込みに行った。数軒回っても出版してもらえないとなれば、自費出版も厭わない覚悟だった。しかし一軒目で本は出版が決まり、N氏と印税についての取り決めが行われた。単純に編集者から本の内容を評価されてのことだった。N氏は安心するよりも、その編集者もあの絵本を知らないことを残念に思った。
本は瞬く間に重版された。N氏の元に舞い込む印税は、時と共に加速的に増えて行った。人生の深みが少ない文字に凝縮されているとされ、一部の教科書に載ることにもなった。
しかし、あの絵本を知るという者の存在は現れなかった。
やがてN氏は老衰し、自分に残された時間が少ないことを悟った。
そうした中、自分の作品が売れることで、盗作という罪悪感は手に負えないほど大きくなった。
耐えかねたN氏は、ついにある取材で白状した。「あの作品は盗作にすぎない。自分の中から生まれたものじゃない」と。記者は、N氏自身の人生が、その絵本の影響を受けたものだったのだと解釈した。そしてその解釈をもってN氏の作品を見返すと、題名も何より相応しいものに思えた。
『I novel』
N氏は「自分の人生そのもの」という意味で名付けていたが、世間が彼の意図したように理解しなかった。それは彼が生きている間も、死んでからも変わらなかった。
N氏の死後、『I novel』は名作絵本として揺るぎない人気を誇っていた。
一部のファンの中には、生前N氏が影響を受けた土地を巡ろうと、彼が通っていた保育園に訪れた者もいた。
現在の園長は彼らを歓迎し、決まって本棚に通すのだった。本棚には、古いものから新しいものまで、あらゆる絵本が並んでいる。それは職員が気に入っている絵本を持ち寄って出来たもので、古くなったからといって捨てられることはほとんどない。
だがその中に、『I novel』と同じ内容の本は一冊として無い。読者たちは必ず、N氏に衝撃を与えた本を見つけようと園内の絵本を全て読み、分からないままに帰っていく。
その日も、1人の『I novel』愛読者が保育園を訪れていた。彼もN氏の言う絵本を見つけることはできなかったが、質の高い作品を読んで満足していた。
彼が特に気に入ったのは、ある冒険物語だった。
長い間園児に読まれ続け、彼らを楽しませたその絵本。表紙の塗装は剥げて、題名はもう消えていた。
おわり
いいなと思ったら応援しよう!