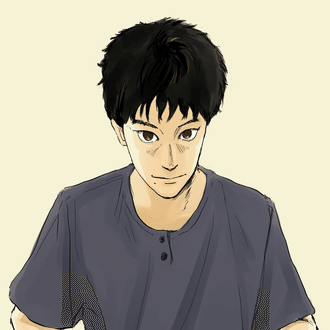『良 いなか』(1840字)
「ええ御守りやんか。祈年祭で売っとってもおかしくないくらいや。ありがとうな」
そう言って田沼先輩が笑った。無人精米機から出て来たばかりの上白米のような、輝くように白い歯を見せる。
「そんな…喜んでもらえて嬉しいです。受験、絶対合格して下さいね」
私は胸の前で両手を握った。先輩もそれに合わせて、ガッツポーズをしてくれる。それを見て、喉に餅が詰まったような気分になった。手をそっと胸に当てる。先輩の合格を願う気持ちは嘘じゃない。だけど、大学が決まれば先輩はこの村を出て行ってしまう。一番近くの大学ですら、ここからじゃ通うには遠すぎるからだ。そのことが堪らなく寂しい。私にとって先輩は、退屈なこのクニの救世主だった。
あと何回会えるだろう。今日みたいに、毎日昼休みに教室に来れば、卒業まであと十数回は話せるかも知れない。だけど私は先輩にとってただの地味な後輩で、先輩は学年でも部内でも高嶺の花だった。釣り合わない。そんな私が先輩に会うには、何かしらの理由が必要だという気がした。誰がお供え物も持たずに山開きのお祭りに来るだろうか。今日は御守りがその“理由”だった。先輩の誕生日は夏だし、バレンタインデーももう過ぎてしまった。私にはもう、卒業式まで先輩に会いに来る口実が無くなってしまったのだ。
毎日は川の水のように流れていく。止めようとしたところで、自分の無力さを思い知らされるだけだ。
今日も6時限目が終わった。箒を動かすフリをしながら、教室の窓から校門の方を眺めた。部活も掃除も無い3年生たちが、校舎から吐き出される。
私はその中に、田沼先輩の姿を認めた。どれ程の人混みの中でも、一目見ればそこにいるとはっきり判る。曇天の夜でも光り続ける、街灯の無い十字路の信号のように。後ろ姿を眺めるだけで、その声が聞こえる気がした。一面の田園で飛び回るツグミの鳴き声みたいに、それは頭の中で響く。
今週末にはもう卒業式がある。それまでに自分から会いに行く勇気も、その口実になる約束もなかった。今ある約束は、卒業式の日、先輩に1冊の本を渡すというものだけだ。それだけが、木守りの柿のようにただ一つ残されていた。先輩と私は本の趣味が似ていた。共通して好きな作家の、そのデビュー作。先輩の受験終了のお祝いも兼ねて、卒業式の日に渡すことになっていた。
先輩が卒業してしまえば、多分もう会えない。それは種を植えていない畑から芽が出ないくらいに、当然のことだった。どうせ最後になるなら。何度目とも知れないその気持ちを、首を振って頭から追い出す。
告白だなんて。カワセミに求愛するムジナなんて聞いたことがない。直接言うことなんてどうせ出来ない。でも、たとえばそのプレゼントする本に手紙を挟み込むくらいなら。駄目だ。そんなことをしたら、今までと同じようには会えない。でも何もしなくても会えなくなってしまうなら。
「ありがとう。この本が受験後の楽しみやってん」
涙で、私が何か言葉を返すことは出来なかった。その本に手紙は、入れていない。それでいいと思う。たまに部活を見にきてくれるときに会えたらそれだけで。
それから先輩は部内、学年内の友達と写真を撮り合い、名残惜しそうに、或いは晴れ晴れしい顔で、ゆっくりと校門へ歩いて行った。
これで、終わってしまう。話しかけるつもりも内容ももう無いのに、足が先輩の方への動いていく。切り分ける前のレンコン丸一本分の距離まで詰め寄ったとき、3年生だろうか、1人の女の子が先輩の元へ駆け寄った。しばらく話した後、先輩は第2ボタンをちぎり取り、その人へあげた。それを皮切りに学年を問わず何人もの女の子、ときどきノリで加わった男の子が先輩の元へ向かい、最後には先輩の学ランは原型を留めなくなってしまった。私は案山子のようにただそれを眺めていた。
そのとき、聞き慣れた声がした。気が付くと先輩が目の前にいた。困った奴らやわ、と言って、学ランに群がるムクドリのような生徒たちを指差した。
「田沼先輩……」
言わなくちゃ。言葉がここまで出ているのに。私は川を塞ぐ大岩を除けるようにして、何とか口を開いた。
「先輩、その本、やっぱり貸すことにしてくれませんか?いつでもいいです。また、いつか、返しに来てください」
それが精一杯だった。精一杯の、次に会う約束だった。
「おお、ええよ。そんときに何かお返しするわ」
先輩が笑った。目の前で、一輪のスイカズラが咲いた気がした。
3ヶ月後。先輩はゴールデンウィークに村へ戻って来た。
部活に顔を出してくれたとき、私に言った。
「あの本、まだ借りとってもええかな?次会うとき返すから」
それから、会うたびに先輩は何か理由を付けて本を借りたままにした。
一年後、本が返ってきたとき、そこには桜色の便箋が挟まれていた。
おわり
いいなと思ったら応援しよう!